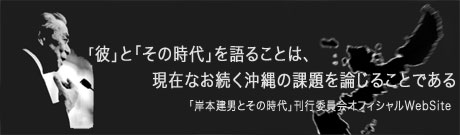
アメリカからペルーへ
#4 アメリカ、君のアメリカ
滞在期間が長くなるにつれて、私は次第にアメリカが好きになっていった。理由はうまく答えられない。このとてつもなく広い社会で噴出している無数の問題と、じかにハダを接しているうちに、やがて魅せられていったとでも言おうか。さまざまの問題が、それぞれの現象形態をとりながら、次々に混とんの度を深めていくように見える状況に、初めのうちは「めまい」に似た感じを覚えたけれども、どちらかと言えば秩序よりも混とんを好む性格が、この現実にうまく適合したのであろう。
ここには、かつてドヴォルザークが表現しようとした瑞々しさはもう無い。たとえば、70マイルの高速で飛ばす大陸横断バスの窓から、一日中同じ情景をながめていなければならないオクラホマの大牧場や、テキサス、ニューメキシコの大平原地帯でも、目の届く限り完璧に鉄条網の囲いがなされていて、これ以上伸びていく余地は全く見当たらない。平原をよぎる嵐や、きらめく稲妻は、「被害総額何万ドル」という形で数字に換算されるだけなのである。
「西部へ」という言葉に象徴されるようなフロンティア・スピリットは、建国と共に国民の中にあり、この国の持つ可能性を示していたわけだろうが、その精神は、いまや実現の場を失っており、おそらくそのことは、国民の精神のどこかに深い影響を与えているはずである。ジョン・ケネディの「ニュー・フロンティア」は、実際のところ行き場が無く枯渇してしまった精神を、形を変えて蘇らせようとの意図を持っていたが、しかし、「ニュー・フロンティア」と「ニュー・ゼネレーション」との結合がもたらしたものは、十年後の若者たちによる「反乱」でしかなかった、アメリカの「フロンティア」が、かつてのように瑞々しく躍動を許される空間は、もう世界のどこにもありはしないだろう。
「フロンティア」の挫折がどのような形で国民に影を落としまたそれと現在の混とんとした状況とが、いかなる関係にあるかを分析することは、私の手にあまる問題である。ただ言えることは、「フロンティア」がまだ息づいていた青年期アメリカにおいて、急速な発展に伴う資本主義の諸矛盾は、横へ拡大していくことを可能にした地理的条件を一つの安全弁として、表面化を押さえられてきたが、その時期を一気に経過することによって、いまだに青年期の爆発力を内包しながら無数の問題が地平線上に姿を現してきたということである。
果てしない未来に続いているように思われたこの国も、いまでは全身を引きつらせている巨人を思わせ、解体を予感させる巨大な歯車にも似たこの国の複雑な問題を考えるたびに、トインビーのいう文明法則が脳裏をかすめる。すなわち一つの文明は必ず衰退期をむかえるということ。
私はあまりに先走った独断に陥っているのだろうか。
この混とんの季節を、政治的に乗り切っていく方法があるとすれば、それは何か。ニクソンが、いまでは言葉そのものの持つ厳格な理性の響きを失って、血の臭いのしみた「法と秩序」(Law and Order)を選択したことは、決して不思議ではない。権力は、文明の危機という事態にあっても、他の方法を知らないだろう「法と秩序」の政策が、典型的なアメリカ人を代表するといわれる中産階級を背景にして、強力に遂行されていくならば、現在の混とんは、「体制と反体制」というアメリカ社会がこれまで知らなかった二分法で、整理されていくかもしれない。いかにも単純な言い方だが、政治の言葉は大体において単純である。
この国の混とんはどこに向かって収束していくのだろうか。しかし、私はこの国の未来を占うことには興味がない。旅人の未来占いなどあたるはずもないし、第一意味が無い。アメリカを去るいま記憶の映像幕に浮かんでくるのは、この状況を生きている者、あるいは耐えている若者たちの顔である。私は、何度か彼らと状況を共有しているような錯覚に落ちたが、いまでは遠い出来事でもあったかのように、距離をおいて見ているようだ。
「女房、子供のことを思えば、体制(Establishment)に入り込むことを考えなければならない」と言ったワシントンのG。「体制の持つ力は、反抗そのものさえ自らの補強物に変えてしまうのだから、大切なことは体制から離脱することである」と話していたロサンゼルスのS。切符を無くして困っていた私を、親切に拾ってくれたニュー・オーリンズのKは、トラックのフロントガラスに「I Like Spiro」(スピロ・アグニューが好き)と書かれた小さなポスターを貼りつけ、胸には星条旗をデザインしたバッジをつけていた。
ラ・グランジの町で車を待っている私に、自慢げにマリファナを見せながら粋がっていた黒人の少年たちは、パンサーの写真を食い入るようにのぞきこんだが、いまはどうしているだろうか。警察官との銃撃戦に備えて、窓をすべて内側から土のうで固め、壁には十数丁のライフルを立てかけてある事務所の中で、「黒人のために死ぬならかまわない」と静かに言い、壁に張ったゲバラのポスターに書きこまれている有名な文句を私に示し、ライフルの撃ち方まで教えてくれたワシントン・パンサーのFは、まだ生きて活動しているだろうか。
シカゴの民主党大会のとき、街を占拠した武装警官を見て、「これがアメリカなのか」と疑ったというPは、希望もなく南米に文化人類学の研究に行くと語り、「これは逃避だな」と言って寂しく笑った。
彼らすべての友人たちに、もう再び会うこともあるまい。そしていま。状況の深みの中で生き続けるであろう彼らと、彼らのアメリカに別れをつげよう。さらばアメリカ、君のアメリカ。

