![]()
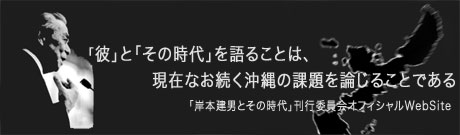
1969年
沖縄タイムス掲載 早稲田大学大学院在学中の文章
現代をどう生きるか 5
反戦のとりでを築く
戦争体験、沖縄闘争の課題
岸本建男
記憶の糸を懸命にたぐっても、敗戦後の混乱期すら浮かんではこないのだから、僕にとって戦争体験は皆無であるというべきだ。だから激烈な戦闘の中で人々を襲ったであろう様々な心理とは無縁であり、また、敗戦を境とする「価値」の崩壊とも関係がない。従って、太平洋戦争の多くの部分については、追体験によってしか知りえないのだが、追体験が常に限界をはらみ、体験の持つ「実感」的な要素を抜きにして成立するものだとすれば、僕の追体験は主要な点において体験とは決定的に異質なものなのに違いない。
以前には体験と追体験との落差に対する認識は、体験世代からあびせられる言葉によって屈折し、いわば劣等感のような形で内部に凝縮されていて、戦争批判や責任に関することを口にするとき、気遅れを感じさせずにはおかなかった。だが、その事は他方では、「戦争の問題」を避けて通ることを可能にするある種の「気楽さ」の原因でもあったといえる。
それゆえに「二・四ゼネスト」の圧殺と、その後に現出した状況がなければ、あるいは、沖縄戦の意味を自分なりにとらえ返すことなしに沖縄闘争を理解しようとしただろう。しかし僕はいま、追体験に伴う弱点を十分に認めた上でなお戦争体験の意味を繰り返し問い続けていかなければいけないと考えている。それは、もちろん「ゼネスト」の提起した思想的課題が、戦争体験の思想的課題と深く結びついていると考えることに起因する。
戦後二十数年の間に、太平洋戦争が「批判」と「責任」の観点に照準を合わせて論じられることは、ごく少数の例外を除いて沖縄にはなかった。ゼネストの圧殺は、このような思想状況の延長上に実は予定されていたとさえいえるのではないだろうか。反戦闘争としてのゼネストが貫徹されるためには、少なくとも「移駐の感触」がその確実性をうんぬんされるのではなく、かかる口実を苦しまぎれにせよ設ける人達の、「戦争」を追いつめているという条件が不可欠であったのだ。
思想の原点を戦争体験に置き、以後の活動がそれによって規定されていると言われている人たちが、個々人の「原体験」から反戦思想の構築を志向することなしに、自らの情念を「祖国」へのどうけいへと収斂させていった事実は、ここにおいて弾劾の対象とされなければならない。むろん、「戦争の問題」をネグレクトしてきた僕自身も、十分に批判の矢をあびるべきだし、とても無罪でいるとは考えていない。
「二・四ゼネスト」は、これまでの「復帰運動」を支えてきた思想を根底から問い返し、これまでの闘争に一応のピリオドをうつ必要を痛感させるものとしてあった。その意味で、大胆に言えば、沖縄闘争は「二・四」を分岐点として前史と後史に分かたれる。それ故に、目前のスケジュールに追われて、或いは急迫した「70年」に焦って、前史の思想的総括と後史の思想的位置づけを回避することは許されないし、「圧殺」の意味の過小評価は危険である。少なくとも運動史を戦争体験との関わりにおいて再評価する姿勢が重要だと僕は考えている。
太平洋戦争の最終局面で戦われた沖縄戦は、結果として沖縄の人々を犠牲者の地位に置くものであったのだが、それでは、満州事変に始まる「十五年戦争」の全局面において、人々は犠牲者であり被害者にすぎなかったのだろうか。断じて否。
異民族の徹底的搾取に加えて、天皇制国家の抑圧体系としてのヒエラルキーの持つメカニズムは、底辺の大衆に作用して、中国、朝鮮その他の人民が、格好の抑圧委譲のの対象となったことを今日われわれは熟知している。沖縄の人々だけが直接、間接の下手人ではなかったと誰が言えよう。日本国民たることを選択し、自らの上昇意識を天皇制国家への「同一化」に求める過程で、わが県民は、侵略国家の国民たることを必然的に選択した。そのことは日常生活そのものさえも加害者としてのそれでしかなかったことを意味する。
そのような形でしか沖縄を組み込めなかった日本の近代化に対してなされる批判は可能だろうし、一定の正当性を持ちうるかもしれない。また、時代的制約を受ける人間の行為の限界も認めなければならない。しかし、沖縄の人々が選択してしまった加害者としての立場は、そんなことで清算されるものではなく、沖縄戦の悲惨によっても拭い去ることの出来ない刻印を我々に押した。沖縄戦の死者たちが、たとえば「むごたらしい死」を死んだことによって決して「やすらかにねむ」れないのと同様に、日本国民としてわが県民による行為がもたらしたおびただしい人民の「死」は、絶対にあがなわれないものであることを幾度でも思い起こすべきである。日本人としてあることによって、すでに一人の「醜い日本人」として告発されるしかない自己の認識が、どのような痛苦を招こうとも、そういう存在でしかない自己への認識を、いわば「負の原点」に据え置いて、そこから戦争を見ていく視点を欠落させてはならないだろう。沖縄における戦争責任論のほとんどは、この認識を欠いていなかったか。
大衆にとって、戦争責任は窮極的には「死」の形で訪れた。生き残った者、後に生まれた者にとっての責任とはこのとき何か。端的に言えば、「戦後」責任にそれは他ならない。主体との関わりで責任を問題にすれば、それでしかありえない。そこから本来の戦争責任論は、反戦思想の構築と行動の提起というきわめてアクチュアルな課題に踏みこむものであるはずだ。
「戦後」史としての復帰運動史をめくれば、この課題に真けんに取り組もうとした多くの証しをみることができるのだが「二・四ゼネスト」の破産へと導かれるこの運動史は、戦争批判の思想と行動にとって必須な要件が、それとして取りあげられていないことを明確に示している。沖縄戦の体験から否応なしに突き当たる国家論の究明は、ここでは民俗の論理にすり換えられ「祖国」への「回帰」を無条件の前提とする「ナショナリズム」が闘争の内実と方向を逆に規定している。一定程度の戦争批判を出発点にしていた闘争のしそうは、平和の理念を戦いのエトスとしてもつことによって「祖国ユートピア」を媒介として発生した手段的、相対的「ナショナリズム」が、平和主義とシェーレを起こすことを防いだけれども、「ナショナリズム」による逆規定は、闘争の思想から国家の視点をずり落とした。かくして「祖国」への郷愁はその裏面に怨念をべっとりと付着させたままで、国家権力を恋慕う。
「祖国」への無自覚な同一化は「解決」であるか。
太平洋戦争の特殊沖縄的体験は、本土と沖縄との関係のみならず、国家と人民、支配者と大衆の関係も明らかにした。従って、国家、国家体制と戦争、支配層と戦争との連関を無視することは賢明ではない。太平洋戦争の本質が本土と沖縄の悲劇的関係という単純な理解の枠組の外にある以上、沖縄戦の体験を本土不信に還元したり、平和の希求を単純な本土憧憬にいまだに逆転させていることは、戦争の問題をあまりに矮少化してしまった結果の盾の両面にすぎない。そこからは、せいぜい「差別の論理」に裏打ちされた「国家」への横すべりの同一化がまたしても結果するだけだ。
日本帝国主義の発展の先端に現出した沖縄戦の批判を基底に据え、更に、再びあらたな帝国主義的再編を目指す、「国家」と「沖縄」との絡み合いを抉り出すことを通して、戦争批判は完了すると考える。従って、「戦後」責任としての「戦争」責任を果たすことは、かかる「国家」と対決していかざるをえない反戦の戦いを、如何に組み上げるかという点から歩を進めるより他にないだろう。そのような存在としての自己責任をいわば「正の原点」として、「負の原点」との複合的視点から、戦いの思想を構築していくことが、僕自身の課題としてあるだろう。象徴的に言えば、わが内なるひめゆりの塔を如何にして反戦の砦に転化するか、である。(早稲田大学大学院)

